求めることと望まないこと 自由死の議論のジレンマ
2019-05-22
前回の「自由な生き方、自由な死に方 〜スイスの「終活」としての自由死」につづき、スイスの自殺ほう助に対する社会の理解や議論の展開についてみていきたいと思います。
スイスでは、自分の死についてもより自由に決めたいとする声が強まってきており、2014年ごろから、健康上に特に問題がなくても死にたいという強い願望がある人に対しても、自殺ほう助を公式に認めるべきだとする、自殺ほう助の条件の緩和を求める動きが強まってきました。
そのような「自由死」を求める動きが強くなってきた一方、他方で、それへの是非は現在、社会でも分かれています。代表的な追いながら、現状と今後の議論の行方について概観してみます。
医師たちの対処
自殺ほう助は、自殺ほう助を受ける人とそれを手助けする自殺ほう助団体だけで、完結されるものではありません。これらの人を言ってみれば当事者とすると、当事者以外の人たちで、自分の意志に関係なく、自殺ほう助に実際に関わる人たちがいます。医師や家族、介護施設のスタッフなどがその典型といえますが、その人たちは、自殺ほう助や、今回の自由死について、どのような対処をとっているのでしょう。
まず、医師の動向をみてみます。
スイス医学アカデミーの2013年の調査(SAMW, 2014)によると、認知症の人に対して自殺ほう助を認める見解に対し、賛成は10%、どちらかといえば賛成が19%。反対は41%、どちらかといえば反対が24%でした。高齢の健康な人の自殺ほう助について賛成票はさらに低く、賛成(8%)とどちらかと言えば賛成(12%)あわせても2割にすぎず、逆に、反対(56%)、どちらかといえば反対(20%)としたのは、8割近い人たちでした(SAMW; 2014, S.1768)。これをみると、「高齢の自由死」について医師の大多数が反対していることがわかります。
そもそも、自由死以前に、自殺ほう助についても、医師は複雑な心境であるようです。アンケートに回答した全体の4分の1にあたる1318人の医師のうち一番多かったのは、確かに、基本的に自殺ほう助を許容でき、個人的に自殺をほう助するような状況を想定することができるという意見で、半分近い医師がこう回答しています(自殺ほう助を認めるが自分ではしないと回答した人は4分の1、自殺ほう助を基本的に否定する人は5分の1でした)。
一方、具体的な状況で自殺のほう助をする準備ができている、と答えたのは全体の4分の1にとどまりました。この一見矛盾しているようにもみえる回答から、多くの医師たちは、一般論として医師が自殺ほう助に関与する必要性を認めつつも、個人的には躊躇が強いことが伺われます。
このような医師の態度には、複数の理由があると思われますが、一応、医療倫理指針(自殺ほう助についての法的な詳細の規定がないため、医学アカデミーが、2004年に「人生末期の患者の看護」というタイトルで定めたもの(SAMW, 2004))はありますが、実際に自殺願望の患者を目の前に、なにが「公平」で「中立」で「正しい」医師の立場や判断になるのかがいまだ明確とはいえないことが、最大の理由ではないかと思われます。
一方、2017年において自分たちが関わった自殺ほう助の4分の1が、すでに「高齢者の自由な死」に相当するものだったと、スイス最大の自殺ほう助団体「エグジット」が表明しているように、実際には、終末期の患者だけではなく、健康上特に問題のない自殺希望者にも自殺ほう助がすでに実施されています。厳密に医療倫理指針と協定で定められている標準規定を厳守していれば、無理なはずなのですが、医師の審査・判断という部分がグレーゾーンとなって、倫理指針に背くことが実際には常態化していることになります。
このような倫理指針と現実が乖離する実情を前に、医学アカデミー(SAMW)は、重い腰をあげ、これまでの医療倫理指針を大きく見直し、終末期の患者に限らず「堪え難い苦悩」がある人全体を対象にするという、医療倫理指針の緩和を2018年5月に打ち出しました。
しかし、医学アカデミーとはまた別の医師の団体のスイス医師会(FMH)が、これに反対の態度をとります。通常、スイス医学アカデミーが定める医療倫理指針を、スイス医師会が医師の職業規定に取り入れ、スイスの医師に通達するしくみなのですが、同年10月、医療倫理指針の改定版を職業規定に組み入れることを拒否したのです。これはきわめて異例の事態であり、現在、医師の間で、自由死を認めるか、どこまで認めるかで、意見が大きく割れていることを物語っているといえます(Brotschi, 2018)。
ちなみに、新しい医療倫理指針は職業規定に取り入れられませんでしたが、現行の医療倫理指針は依然有効であるため、自殺ほう助団体は、これまでと同様のやり方で、自分たちの活動を続けています。
一方、自殺ほう助でも緩和ケアでもなく、絶食死を別の選択肢として提唱する医者もでてきました。この方法で死に至るまでは通常三週間かかりますが、徐々に絶食死の事例は増えてきており、今後絶食死は、自殺ほう助や緩和ケアと並行して「社会の大きなテーマMegathema」になると予想されています(Müller, 2017)。

ホームのスタッフたちの対処
現在、スイスにはホーム(ホームとは、ここでは、老人ホームと介護施設を合わせたものを示しています)が約1600施設あり、全国で約10万人の収容が可能な状況が整っています。以前は、70歳を過ぎたくらいで健康でもホームに入ってくるような人がかなりいましたが、今日は、在宅が不可能になってから施設に入ってくる人がほとんどであるため、ホーム居住者の高齢化が進んでいます。現在、スイスのホーム入居時の年齢は、平均年齢84から86歳です。つまり、多くの入居者にとって、ホームは事実上終の住処となっています。
ホームでの自殺ほう助事情は、州によって異なります。自殺ほう助を権利としてみとめ、居住者が希望すればホームでの実行を拒否できないとする州もあれば、各施設に、許可するか否かの決断を委ねている州もあります。ホームでの自殺ほう助を全面禁止にしている州も少ないですがあります。2014年、エグジットによる自殺ほう助583件のうち60件がホームで行われました。
大勢の人が共同で暮らし、同室に複数で住んでいることも多いホームでは、自殺ほう助がまわりに与える影響も、大きくなりがちです。
自殺ほう助後に検察官や警察が現場検証に訪れるため、普段の穏やかな雰囲気が乱れるだけでなく、自分が生きる意味を感じられなかったり、ほかの人に迷惑をかけているといった気持ちをもつ居住者に、不要な圧力や不安が生じないように、通常以上に気遣いが必要となります。自然死でなくなる居住者と異なり、自殺ほう助で亡くなった居住者については居住者への通知を最小限にとどめる処置をしているところもあります。
介護スタッフにとっても、検察官の現場検証に立会うなど、通常業務以外の負担を強いられるだけでなく、担当する居住者が自殺ほう助したことで個人的に責めを感じたりしないよう、配慮が必要になるといいます。
国内に2600ヶ所の老人ホームと介護施設の統括組織クラヴィヴァCuravivaが行なったルツェルン州の匿名のアンケートでは、ホームの3分の1が自殺ほう助に反対、それについて話す準備がまだできていないと回答しています。ほかの3分の1は、社会の圧力のため、このことについて話すようになったと答え、残りの3分の1はすでに自殺ほう助を行なった実績がありました(Odermatt, 2018)。
家族の気持ち
家族は、自殺ほう助が起きた時に、医師やホームのスタッフよりもはるかに強い影響を、多くの場合、受けていると思われますが、そのような家族は、どんな思いで、身内の自殺ほう助による死を受け止めているのでしょう。
とはいえ、自殺ほう助団体の言動についてはメディアの注目度が高く、その主張を聞く機会が多い一方、自殺ほう助で家族をなくした人々の声を聞くことはまれです。どんな形であれ家族を失った人の喪失感は大きく、公的に意見を述べるというエネルギーやモチベーションを持ち合わせている人は少ないでしょうし、まして、故人の自殺ほう助に、個人的に反対であった場合、故人の意志を尊重したい気持ちと自分の気持ちの間に葛藤も生まれ、それについて公に語られることは、少なくなるためでしょう。
だからといって、自殺ほう助という選択肢によって身内が「自由死」した家族の心境が、軽視されていいわけではないでしょう。このため、自殺ほう助の家族への影響について調べた数少ない研究として、チューリヒ大学の臨床心理学者ヴァグナーBrigit Wagnerの調査結果は示唆に富みます(Wagner, 2012)。
ヴァグナーは、調査時点から遡って14〜24ヶ月前に、家族や近しい友人の自殺ほう助に立ち会った人を対象に調査をし、85人の回答内容を分析しました(これは、自殺ほう助で家族をなくした人々がすべて対象であり、(健康な人々の自殺ほう助である)自由死で家族を無くした人にとどまりません)。この結果、13%がPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状、6.5%がその前段階の症状を示し、うつ病の症状と判断された人は16%でした。自殺ほう助で家族を無くして2年近くたっても、PTSDやうつ病に苦しんでいる家族が4割近くいることになります。
この調査の回答率が51%と低かったため、これだけで全体像を判断するは難しいものの、自殺ほう助が立会った人にとって心理的に長く重い負担になっていると著者は指摘します。
これに対し、エグジットで長く自殺ほう助に関わってきたフォークとHeidi Vogtは、協会としては、早い段階で家族と連絡をとるよう会員にうながすなど、家族への一定の配慮をしており、亡くなって2〜4週間した後にも家族に連絡をとっている。現実に、半分以上の家族は協会とコンタクトを受け入れており、うつ病やトラウマになるケースは自分たちのところではほとんどない、と反論します。また、自然死で家族がなくなった場合の同様の調査がないため、この研究だけで内容を評価することは難しいとします(Freuler, 2016, Exit wehrt sich, 2016)。
デグニタスでも、自殺ほう助を願う人たちに、家族や友人の承認をできるだけ求めるようにうながしたり、自殺ほう助の日程を知らせ、家族や友人に最後まで立ち会ってもらうことで、喪失を受け入れやすくしたり、別れを可能にするなど対処をしています。
自殺ほう助団体が、家族への配慮をし、支援活動も行なっているのは確かでしょう(柴嵜、59−60頁)。とはいえ、自殺ほう助団体側から提供するそのような配慮や救済事業が実際にどれだけ、自殺ほう助による死を家族が受け入れる助けになっているかは、別問題として残ると思われます。
ちなみに、オランダでの研究では、自殺ほう助の場合と異なり、緩和ケアが家族に与える悪い影響は見当たりませんでした(Freuler, 2016)。
社会への影響を危惧
自由死の議論が難しいのは、それ自体の是非が見極めるのが難しいからだけでなく、自由死という考えが社会に広がることで、社会のほかの部分にも間接的に、しかし少なからぬ影響を与えることが危惧されるためです。
例えば、スイスのカトリックの頂点にたつゲミュアFelix Gemürは、現在の自殺ほう助の向かっている方向が、「わたしには、健康で、生産的で、スポーツができ、まだ自分ですべてできる人だけが、生きるに値する、そんな風に言っているように思える。これは、我々の社会での、障害を持つ人や弱者、生産的でない人や貧しい人を締め出そうとするひとつの傾向だ」(Boss/ Rau, 2018, S.17)と、警鐘を鳴らします。
スイス医師会の医学雑誌『スイス・メディカル・フォーラム』でも、「経済的な理由で「死にたいと思うべき」圧力が並行して生じて、自殺ほう助が高齢化社会の政治的な装置になる危険性は、否定できない」と認めます。そして、高齢者が急増する人口変動に並行して、今後、性急に、別の提案をつめていかなくてはならないと提言しています(Zimmerman, 2017)。
自殺を抑制する効果
一方、自由死が認められることで、精神的にむしろ安定するような作用を、人々に及ぼすという事実も見過ごすことはできません。
35年以上スイスで公式に活動を行なっている自殺ほう助団体のおかげで、自殺ほう助件数は増えている一方、自殺ほう助団体の会員となった人たちの間で、会員になったあとに、自殺をとどまる、いわゆる「自殺抑制効果」と思われるケースも少なくありません。
例えば、二回の医者の診断で暫時的に自殺ほう助が可能という判断が下すことを、自殺ほう助団体「ディグニタス」では、暫時的な「青信号」と呼んでいますが、この「青信号」がでた後、70%の人からはその後一切連絡がこなくなり、16%の人は、自殺ほう助の必要なくなった旨の連絡をしてくるといいます。そして最終的に自殺ほう助を望むのは、会員の3%に留まるといいます(Dignitas, Lektion)。
エグジットに登録した人の間でも、よく話し合いをした結果、自殺ほう助を受けるのをやめるケースが多く、全体の80%の人たちは、緩和ケアなどの別の解決策を最終的に選択しています(Mijuk, 2016)。
老人ホームや介護施設(以後は、これらを合わせて「ホーム」と表記します)でも、居住者が、自殺ほう助の会員になることは、実際に実行するためというより、むしろ、これでなにかあったら頼めばいい、という安心感を得るための一種の「保険」のようなものとなっているようだ、という意見を聞きます。
このような状況をふまえて、ディグニタスの会長ミネリLudwig A. Minelliは、自分たちのやっていることが、「自殺ほう助よりもずっと広いもの」であり、自殺予防にもつながっていると強調します。「包括的に相談することができ、困難な状況でも選択肢があれば、人は、プレッシャーやストレス、苦悩が減り、これにより、よりよく長く生きることができる」(Stoffel, 2017)というのが、持論です。
また、スイスの自殺件数は全体として、過去20年減り続けています。自殺の減少と自殺ほう助の増加の間の関係が明確になっているわけではありませんが、自殺願望者の一部が、暴力的な自殺を自分で試みる人が減るかわりに、自殺ほう助団体を通して自殺を実施している人が増えていると推測されています。それを、苦痛を伴う残酷な死に方や、死ぬことができる重い後遺症を追って生き続ける人を減らすことにもつながっている、と解釈することも可能であり、このため、外国人会員のそれぞれの祖国で自殺ほう助も受けられるようになり、「我々がしていることを、医療や社会システムに統合されるようになれば、ディグニタスやエグジット、ほかの同様の組織は安心して消え去ることができる」のだ、とミネリは言います (Stoffel, 2017)とも言います。
いずれにせよ、老年医学専門家のボスハルトGeorg Bosshardは、自殺ほう助が占める死因の割合はこの先も上がっていくだろうとします。2014年の時点で自殺ほう助による死亡は、全体の死亡の1.2%にすぎませんが、10年後には、(自殺ほう助も医師の積極的安楽死も認められている現在とベルギーのフランドル地方の同レベルの)5%程度になるのではないかと予想しています(Mijuk, 2016)。

おわりにかえて 〜今後の議論の行方は
スイスでは自由死の権利の拡張(自殺ほう助の自由化)を求める議論は、新たな社会のコンセンサスに近づいているというより、ジレンマが鮮明になり、むしろ膠着状態に陥っているようにみえます。
しかし、いずれにせよ、社会において、自殺ほう助の「賛成者でも反対者でも誰もが、人が死ぬ意志にプレッシャーをかけてはいけないということでは、一致していることは確か」(Vollenwyder, 2015)です。ここを議論の出発点にして、「自由な死」については、早急に結論を出すことに終始せず、立ち止まり状況を再点検することが、今、スイスに必要なのかもしれません。
倫理学者ビラー=アンドルノNikola Biller-Andornoは、自分の死を個人的に決定することは容認されるべきであるにせよ、ひとつの決まった答えがあるわけではなく、誰もが自分で人生末期を積極的に形作る必要はない。自分で決めずに、医師や家族に委ねるのも可能だといいます。そして「人生末期において最も重要なものは寛容さ」だと強調します(Biller-Andorno, 2015)。
ここでいわれる、人生末期における寛容さとはなんでしょう。まず、緩和ケアや絶食死など、最近新たに注目されるようになった選択肢も含め、様々な死の形を認め合う社会全体の寛容さを指しているでしょう。
一方、もう一つ重要な方向に向かう寛容さも、含まれているように思います。これまで比較的健康や社会的な環境に恵まれた若い高齢者たちであっても、これから先、後期高齢期に入っていけば、当然、これまでと異なる、健康や精神面でのアップダウンを体験することになります。その時に、これまで同様自分で死に方も決めるのがいいことだと考えることも、ひとつの考えですが、自分のなかで意見が揺れ動いたり、自分の判断に自信がもてなかったり、自分で決めることができなかったりする、そんな(決してこれまでの自分と比べて「自分らしくない」かもしれない)自分自身に気づくかもしれません。そんな新しい自分の気持ちも受け止める、自分自身に対する寛容さも必要なのではないかと思います。
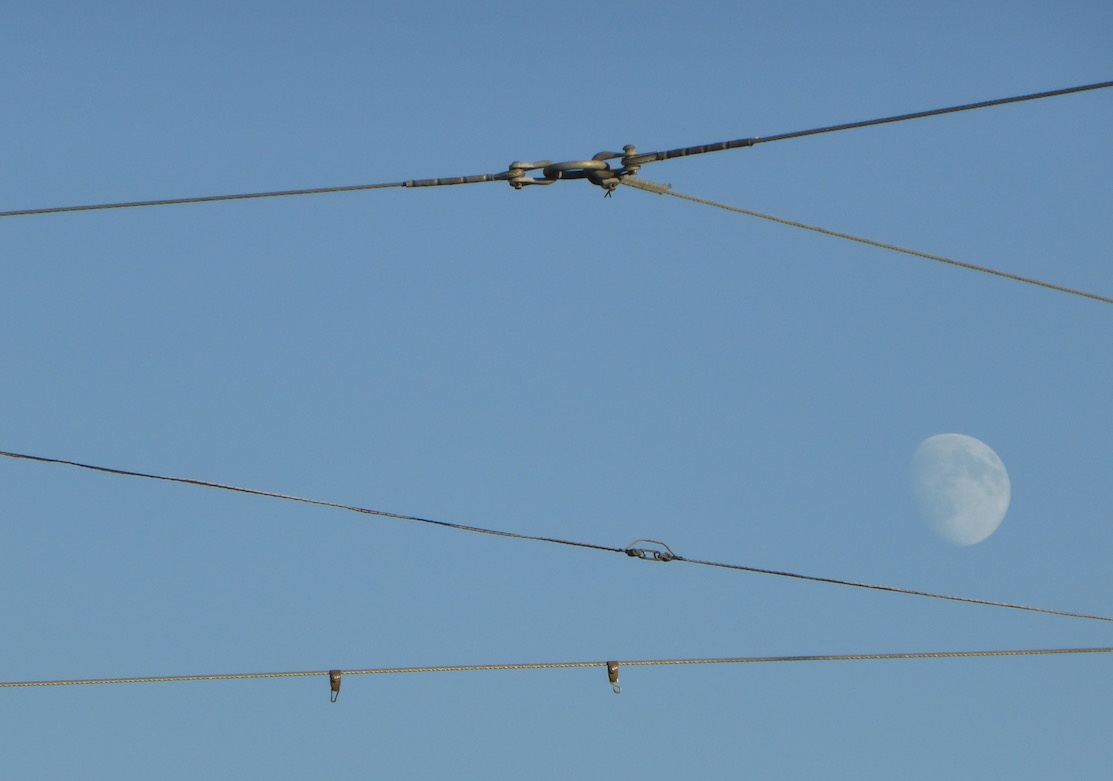
参考文献・サイト
Abegg, Andreas, Zur Zulässigkeit der Zürcher Vereinbarung mit Exit. In: NZZ, 25.7.2009, 10:30 Uhr
Bieler, Larissa M. (宇田薫訳)「死を巡る議論―自殺天国のスイス」、スイスインフォ、2016年07月11日11:00
Biller-Andorno, Nikola, Torelanz am Lebensende ist das Wichtigste, Zeitlupe, 11/2015, S.17.
Boss, Catherine / Rau Simone, “Das Zölibar ist kein Dogmat». Bischof Felix Gemür über sexuelle Übergriffen in der Kirchen und das Geschäft mit der Suizidhilfe. In: Sonntagszeitung, Fokus, 8.12.2018, S.15-17.
Brotschi, Markus, Ärzte wollen Sterbehilfe nur bei Schwerstkranken leisten. In: Tages-Anzeiger, 26.10.2018, S.4.
Enggist, Manuela, 43% wollen den Freitod. In: Schweizer Illustrierte, 22.04.2016.
Fluck, Sarah, «Swiss Option» – Sterben in der Schweiz für 10’000 Franken. In: Der Bund, 4.6.2018.
Freuler, Regula, Das Leiden der Angehörigen. In: NZZ am Sonntag, 18.5.2016, 10:30 Uhr
GV stimmt pro Altersfreitod, Exit, 24.05.2014.
Hehli, Simon, Warum die Schweiz eine Sterbehilfe-Hochburg ist. In: NZZ, 17.6.2017, 05:30 Uhr
穂鷹知美「現代ヨーロッパの祖父母たち 〜スイスを中心にした新しい高齢者像」一般社団法人日本ネット輸出入協会、2016年4月8日
穂鷹知美「対立から融和へ 〜宗教改革から500年後に実現されたもの」一般社団法人日本ネット輸出入協会、2017年10月4日
Kobler, Seraina, Selber entscheiden, «wann genug ist». In: NZZ, 11.3.2015.
Mijuk, Gordana,Der Tod gehört mir. In: NZZ am Sonntag, 4.12.2016, 07:48 Uhr
Müller, Mellisa, Fasten bis zum Tod. In: St. Galler Tagblatt, 15.3.2017, S.23.
柴嵜 雅子「スイスにおける自死援助協会の活動と原理」『国際研究論叢』24(1)、2010年、51―62頁。
Vollenwyder, Usch, Jedem Menschen seinen eigenen Tod. In: Zeitlupe, 11/2015, S.11-15.
穂鷹知美
ドイツ学術交流会(DAAD)留学生としてドイツ、ライプツィヒ大学留学。学習院大学人文科学研究科博士後期課程修了、博士(史学)。日本学術振興会特別研究員(環境文化史)を経て、2006年から、スイス、ヴィンタートゥア市 Winterthur 在住。
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。



