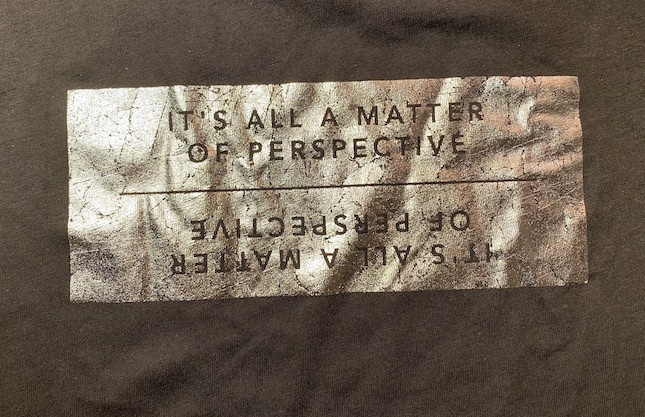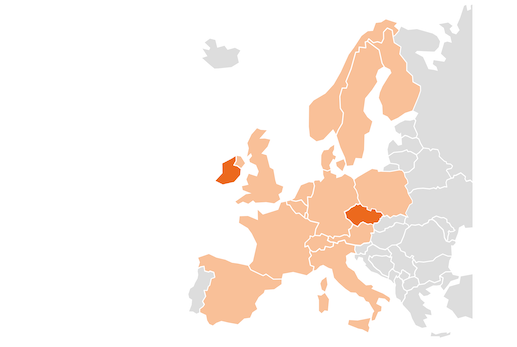ルワンダがロックダウン下で選んだ教育機会最適化のための手段 〜ラジオによる遠隔教育
2021-02-20 [EntryURL]
コロナ危機下の学校閉鎖中に行われた遠隔教育についての連続コラム最終回は、ルワンダです。
※これまでのコラムは以下からご覧になれます。
人口の半分が就学年齢のルワンダのコロナ危機
ルワンダは、東アフリカにある人口は約1300万人の共和国です。2019年から2020年の1年間の人口増加率は2.58% と人口が急増しており、人口の半分が18歳以下という非常に若い国です。
このような人口分布のルワンダにとって、子供たちの教育は、将来の国の明暗を分けるといっていいほど、非常に重要な課題です。しかし、コロナ感染の拡大を未然に防ぐため、ルワンダ政府も、3月15日、すべての学校の閉鎖する決定を下しました。当初は4月末までの予定でしたが延期され、最終的には11月はじめまで、学校が閉鎖されることになりました(11月以降は、クラスに出席できる生徒の人数を制限するなどして、再開しました)。
さて、ここで焦眉の問題となったのは、国全体で300万人以上という、学校に行けなくなった生徒をいかに、学校以外で教育するかです。

ルワンダが選んだ「ラジオによる教育」
結論を先に言うと、ルワンダは、ラジオを通じた授業という選択肢を選びました。
まず、一刻もはやく、ラジオに授業を切り替え再開させるため、ユニセフのルワンダ事務所と協議し、外国で制作された授業プログラムを利用することにしました。これにより、ロックダウンがはじまり2週間の間に、クラスの授業をラジオに移行させることに成功します。
これと並行し、教育関連の非営利団体Inspire, Education and Empower とともに、適切な独自の授業プログラムの作成をはじめました。具体的には、小学校1年から4年までの授業プログラムと、就学前のこどもたちへのプログラムをつくることにしました。
ラジオというと一方的に放送するだけというイメージがありますが、なるべく、インターアクティブに学べるよう、プログラムを工夫しました。例えば、ラジオで、新しくならった言葉をスペリングしたり、書くようにうながします。こどもたちに質問があれば、授業中に、新たに設置された無料のホットラインに電話することもできるようにしました。このようにして作成された授業は、ルワンダの公用語 Kinyarwanda と、数学と英語の三科目で、ひとつのラジオ番組は20分です。
総じて、ラジオで毎日8時半から午後2時の間、授業が放送されるようになりました。昨年8月の時点で、ルワンダの生徒の半分以上がこのようなラジオの授業を受けていました。
世界的にみたコロナ禍の遠隔授業の実情
日本では、NHKや放送大学のテレビやラジオ講座がかなり普及しているので、一度は視聴したことがあるという人も多いのではないかと思います。視聴するだけでなく、NHKの教育講座のテキストを購入するなどして、アクティブに授業に参加したことがある人も、少なくないかもしれません。
他方、昨年、遠隔授業といえば、圧倒的に多く耳にしたのが、インターネットを使ったものでした。少なくとも先進国では、遠隔授業というと、もっぱら、デジタル教材をつかった授業やオンライン授業に照準が合わせられていたように思われます。
このため、このルワンダの話を最初に聞いた時は、私としては、ちょっと新鮮な驚きで、同時に、なるほどその手も確かにあったか、という気もしました。
実際、世界全体を視座にいれて眺めると、世界の就学生(学校に通う生徒)の半分に当たる8億2600万人は、(先進国で想定するようないわゆるネット環境を使った)遠隔授業がうけられない状況にあります。7億600万人は、インターネットへのアクセスができず、5600万人は、携帯電話の電波もとどかないところにいるためです。
そして、そのような、インターネットがなかったり、パソコンなどのデジタル機器が普及していない場所では、今でも、100年以上の歴史をもつラジオや(それよりは新しいもののすでに半世紀以上の歴史がある)テレビが教育ツールとして最も有効となります。実際、アフリカでは70%の国が、ラジオとテレビを使った教育にきりかえ、34%は、それらを併用する形で対応しています(UNESCO, Learning through)。

ルワンダの教育メディアとしてのラジオの意義
ルワンダでは、ラジオの授業のほかに、テレビやオンラインのプラットフォームもつくられていますが、オンラインのプラットフォームで学ぶEラーニングは、当初5000人で、7月には5万人にまで利用者が増えましたが(7月のビデオでの報告 Unicef Rwanda, Connecting )、ルワンダの就学人口全体からみた、アクセスし享受できている子どもたちの割合は、2%以下とわずかです。
これに対し、ラジオは圧倒的にアクセスがしやすいツールです。公共ラジオ放送Rwanda Broadcasting Agency はルワンダの住民の99%、つまり、ほとんどの人にアクセスすることが可能なメディアであり(Nagiller, Wenn das Radio)、国の重要なインフラのひとつです。
このため、コロナ禍にもかかわらず、生徒が家庭で授業を受講することを可能にする唯一の手段として、ラジオ教育が選ばれたわけですが、この方針は、国際社会からも初期の段階から支持を得ることに成功しました。2020年3月にはやくも、ルワンダのユニセフ事務所は、遠隔授業の助成金として、7万ドルの支援を受けることとなり、さらに、GPE Transforming education, Rwanda(助成機関は、世界銀行)からも、2020年から21年の2年間で、トータルで1000万USドルの援助を受けられることになりました。
このような潤沢で迅速な支援金のおかげで、オリジナルの教育プログラムの開発も早期に着手されることになり、それが、最終的に、ラジオ授業の受講の割合を押し上げることにもつながったといえるでしょう。
もちろん、ラジオでの授業には、制限がつきものです。視覚的に学ぶことができませんし、同時にさまざまなレベルの授業や違う科目を学ぶこともできません。このため、インターネットやテレビでの遠隔授業に比べ、学べる質や量も多分限られてくるでしょう。また、生徒の半分以上がラジオ講座を受講したのは確かに輝かしい実績ですが、多様、実際にその習熟度はどれくらいであったかはまだわからず、その結果もふまえて評価しなければ、最終的な授業の質の評価とはいえないでしょう。
それらの指摘はすべてもっともで100歩ゆずるとしても、それでも、ルワンダがラジオに力をいれる方針をとったのは、評価されるでしょう。学校閉鎖という危機的な状況にあって、ベストではなくても、ベターな道であったと思われるためです。
それぞれ国や社会によって、遠隔授業の前提となる状況は異なります。電気やインターネットなどの基礎インフラ、利用可能な学習教材の種類(教科書、筆記用具、デジタル機器など)、対象となる子供の人数や年齢層、遠隔授業を支援する準備がある親の有無やそのクオリティなど。ルワンダは、それらの教育インフラを現実的にふまえ、生徒全体への教育機会の最大化に重点をおき、(高質の授業のために、パソコン普及やインターネットの普及を目指すなどに労力を費やすかわりに)、いってみれば現地点の自国の身の丈にあった形で、対応した好例といえるのではないかと思います。

おわりに
3回にわたって、コロナ禍の学校閉鎖にあたって、とられた対策や課題・問題を、違うアングルからみてきました。
ドイツ、スイス、ルワンダ、どの国でも共通して、学校閉鎖は、想定外のことであり、教育プログラムもインフラも全く追いついていない差し迫った状況からのスタートでした。
他方、2回目でとりあげたように、コロナ危機で、緊急に必要なもの、足りない部分が社会で鮮明になり、教育とは無縁にみえた社会の違う方面から、応援する人や動きもでてきたのは、社会にとって朗報でしょう。そこを起点に、これまで教育現場に無縁だった人たちがつながり、地域の教育を支えるしくみが補強されるようになるのなら、素晴らしいと思います。
これまでの約1年の間、どの国も、さんざん、どの学校もコロナ危機にふりまわされてきましたが、せめて、このような、(ポジティブな)コロナ危機の置き土産があるのなら、それはできるだけ多く拾い集めて、これから先につづくウィズコロナ、アフターコロナの時代を、また踏み出していってほしいと思います。
参考文献
GPE Transforming education, Rwanda(2020年1月13日閲覧)
Houser, Veronica, Radio learning in the time of Coronavirus, Unicef, 13 April 2020
UNESCO, Learning through radio and television in the time of COVID-19, 02/06/2020
U.S. Embassy in Rwanda, U.S. Government Supports Children to Learn From Home
穂鷹知美
ドイツ学術交流会(DAAD)留学生としてドイツ、ライプツィヒ大学留学。学習院大学人文科学研究科博士後期課程修了、博士(史学)。日本学術振興会特別研究員(環境文化史)を経て、2006年から、スイス、ヴィンタートゥーア市 Winterthur 在住。
詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。